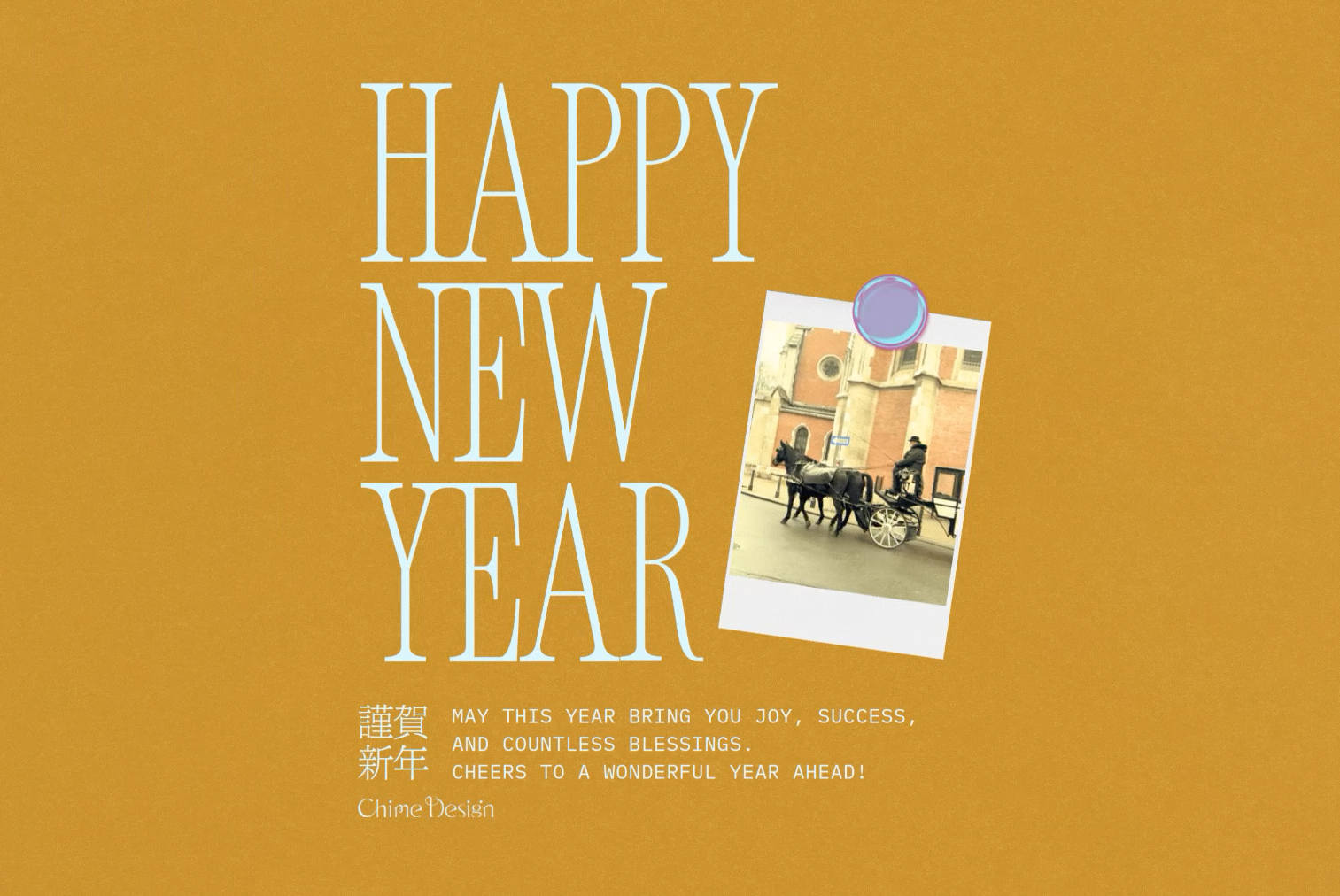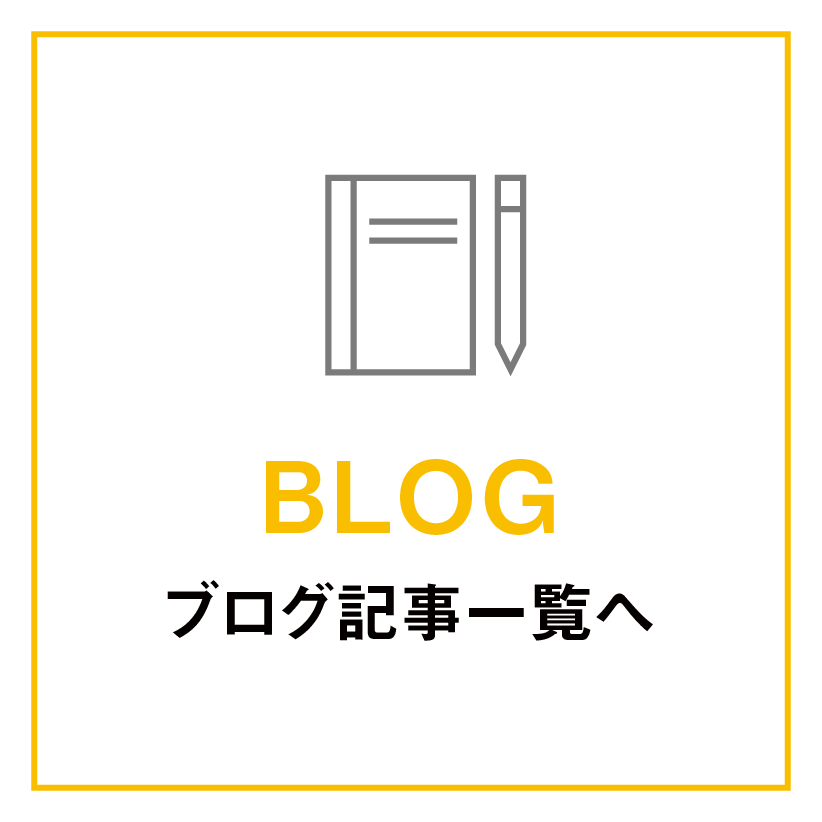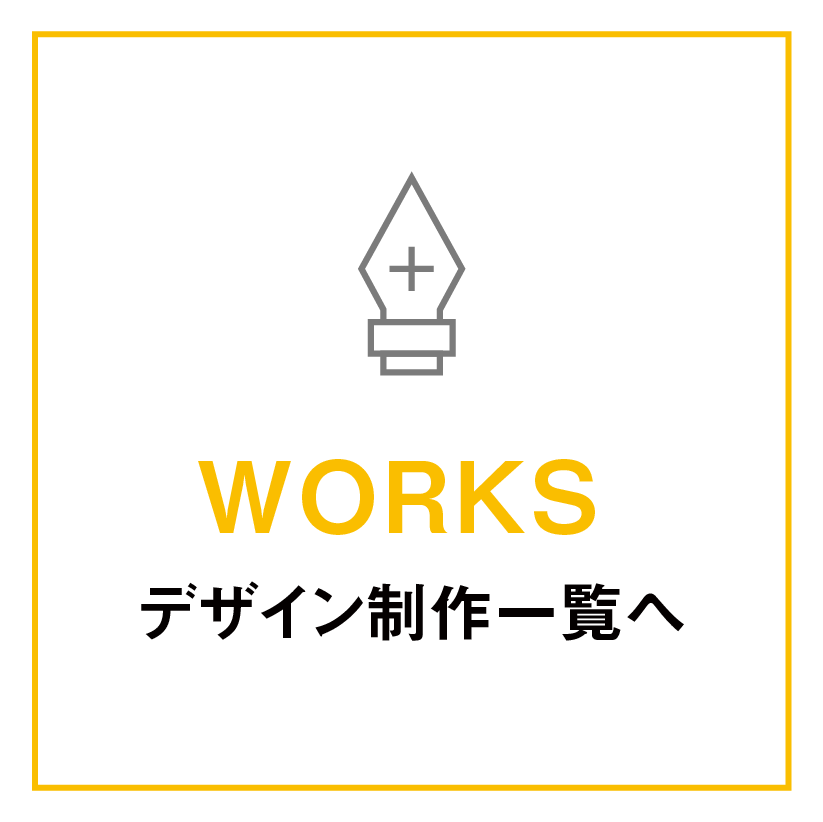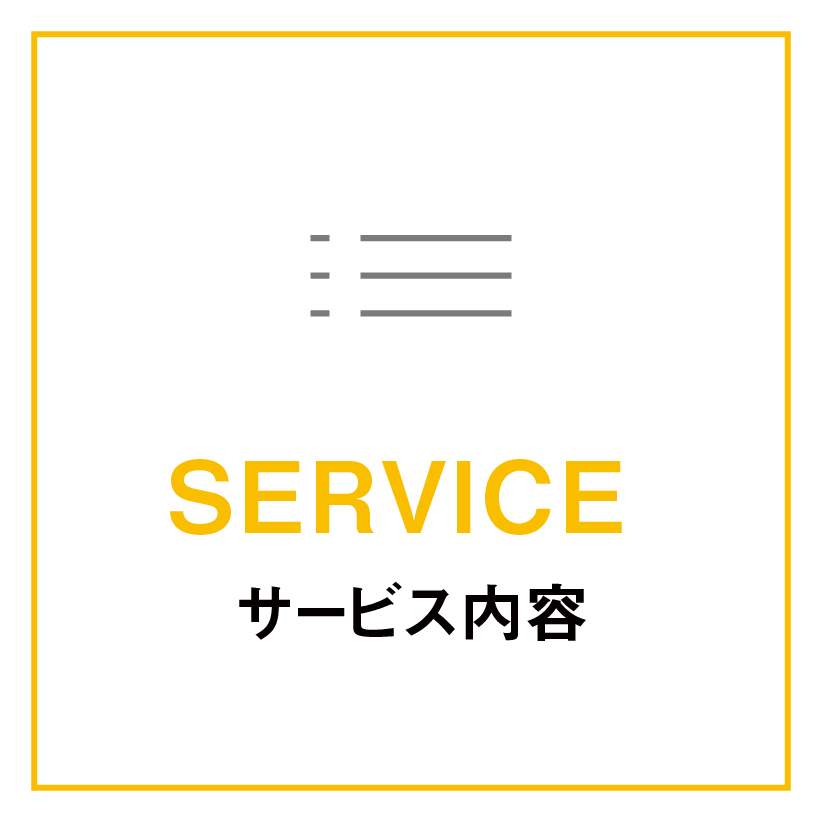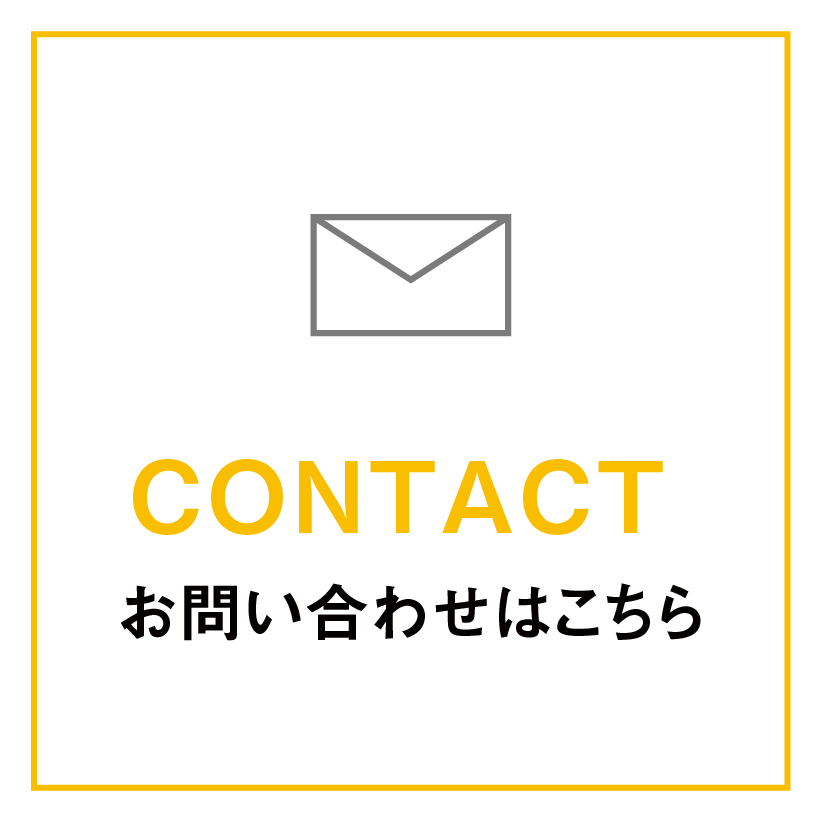23 4月 お茶を学び、五感で感じる総合芸術「茶道」の世界
2021年、イギリスへ渡航する前に「日本文化を深く知りたい」という思いから、茶道のお稽古を始めました。
想像以上に多くの“デザインの気づき”があったことに、驚きと感動を覚えました。
茶室に一歩足を踏み入れると、そこは静寂に包まれた空間。
お湯が沸く音、掛け軸やお花の飾り、お茶菓子の彩り——そのすべてが、五感を通じて私に語りかけてきます。
お茶をいただいたあとは、道具を拝見する時間が設けられていて、茶碗や棗(なつめ)、柄や素材、そしてその背景にある物語や作者の想いに触れることができます。

「空間のブランディング」としての茶道
先生が毎回用意してくださる道具や和柄は、すべてが季節に沿ったもの。
茶室全体が一つの世界観としてブランディングされていることに気づいたとき、私はハッとしました。
デザインの世界でも、色や素材、空気感、視線の流れ——すべてが統合されてはじめて「伝わるデザイン」になります。
茶道もまさに“総合芸術”であり、見る側(客)にも、その背景や意図を感じ取る感性が求められることを実感しました。

公のお茶会に参加して
初めて「公のお茶会」に参加する機会をいただき、佐世保のアルカスにある茶室へ。
参加条件の一つが「着物の着用」だったため、この日を目標に着付けも一から学ぶことにしました。
着物の柄には、季節や意味が込められており、会の趣旨や場の雰囲気に合わせた選び方があると知りました。
私はもともと柄のデザインが好きなので、「意味のあるデザイン」の考え方に深く共感。とても大きな学びとなりました。
そして本番、なんとか自分で着付けを済ませ、無事お茶会に参加することができました。

感じたこととこれから
お茶は単なる飲み物ではなく、五感で感じる芸術体験。
静寂の中にある豊かさ、目には見えない心遣い、そして一瞬の美を味わう贅沢な時間でした。
「想像」と「実際に体験すること」の違いは、想像以上に大きく、深いもの。
この経験を通して、少しでも海外で日本文化の魅力を伝えられる自分に近づけた気がします。
そして、それをデザインにも活かしていける——そんな可能性を感じています。

おわりに
フリーランスのグラフィックデザイナーとして、デザインに必要な「感性」は日々の体験から育まれるものだと改めて思います。
茶道という伝統文化の中には、現代にも通じる美意識と設計思想がたくさん詰まっていました。
自主制作で作っている柄のデザインはこちらからご覧いただけます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

最近の投稿